| 第6回定例講演 (平成29年2月18日) |
尾張藩主の墓石は鵜沼石だった
(高野山真言宗/高家寺住職)北川 宥智
*本ページは、講演時の資料を元に当編集部にて作成したものです。

図-1 講演についての掲載記事(中日新聞 2017/2/21 岐阜近郊)
1.建中寺
建中寺は、慶安4年(1651)第2代尾張藩主徳川光友が、父である藩祖義直の菩提を弔うために建立した寺で、尾張徳川家の歴代の墓所とされてきました。 昭和20年(1945)の名古屋大空襲では、多くの建造物が災禍を免れることができましたが、宗春の墓石の損傷は、この時の焼夷弾の直撃によるものでした。(拡大)

写真-1 昭和20年3月12日の名古屋大空襲の一か月後の東区の空撮
(1945/4/6 陸軍撮影/国土地理院 空中写真閲覧サービスより一部加筆)
写真-1 は、当時の建中寺周辺の写真で、赤でなぞった線が中央本線です。左端に名古屋城が見えますが、この一か月後の空襲で被災したのでした。
現在の地図より、大正時代のもの(図-2)と見比べると、名古屋城と建中寺の位置関係がよく分かります。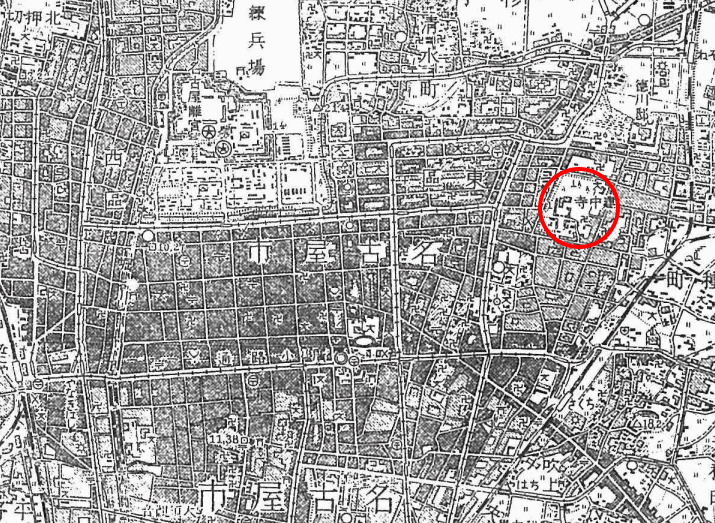
図-2 大正期の名古屋の市街地 (1920 (大正 9)年 1:50,000を縮小)
(国土地理院中部地方測量部資料による)
(拡大)

写真-2 戦後間もない頃の建中寺上空からの空撮(1950 米軍撮影)
(国土地理院 空中写真閲覧サービスより)
2.墓石に使われた鵜沼石
(拡大)

写真-3 石亀神社(2017/2/22撮影)

写真-4 修理された宗春の墓(右)2010
鵜沼石は砂岩の中でも特に堅く、それ故、宗春の墓石も損傷程度で済んだのかもしれません。また、永らく修理されずに放置されていたのも その堅さ故ともいえます。実際、この墓を修理された一級技能士の藤沢さんも、この石の特定には苦労したと述懐されていました。
その鵜沼石の石切場の跡が、石亀神社の中に今も残っています。石亀神社は鵜沼宿から少し北に上ったところにあります。
(拡大)

写真-5 草と落ち葉に覆われてしまった鵜沼石の石切場跡/石亀神社(2017/2/22撮影)
3.徳川宗春 Q&A
(北川住職の講演資料より)
宗春卿は、いつの時代、どのような時代の人?
- 生まれたのは元禄九年(1696年)、元禄文化華やかな時代名古屋生まれ。
- 江戶幕府五代将軍綱吉から十代将軍徳川家治の時代の人。
- 尾張藩主時代の将軍は八代将軍徳川吉宗公
- 映画やドラマお芝居で有名な「忠臣蔵」「江島生島事件」「天一坊事件」等が起きた時代
宗春卿の生まれや地位は?
- 幼名は萬五郎兄吉通より諱を得て萬五郎通春に、元服後は求馬通春に
- 尾張徳川家第三代当主徳川綱誠卿の二十男(第三十三子)<異説あり>
- 母は宣揚院梅津。
遠江横須賀(掛川市)藩本多家浪人三浦太治兵衛(後に犬山藩士)長女 - 祖父は第二代当主徳川光友卿。
- 祖母は三代将軍徳川家光公の長女千代姫。
- 成人した長兄は第四代当主徳川吉通。
- 次兄は第六代当主徳川継友。
- 三兄は、美濃高須藩主第二代当主四谷松平義孝。
- 四兄は、同い年の松平安房守通温(みちまさ)。
- 妹は、五代将軍徳川綱吉の養女で、加賀前田家に嫁いだ松姫
- 若い頃は部屋住み。理由は不明だが、兄に比べるとかなり元服や官位取得が遅れる。
- 久留米藩有馬家二十二万石の仮養子となる。
- 断絶した尾張藩御連枝(ごれんし:分家)の大久保松平家を再興し、奥州梁川藩三万石の大名となる。
- 兄六代藩主徳川継友卿の薨去後、本家を継承し御三家尾張徳川家第七代六十二万石の大名となる。
宗春卿が江戸に下ったのはいつ頃?
- 兄達に遅れること一年、正徳三年(1713)四月に中山道を通る。途中でお畳奉行の朝日文左衛門に声をかける。
- 長兄の藩主吉通に可愛がられ、上屋敷市谷邸の奥住まい夕食は常に共に。
- 二代目市川團十郎が助六を演じる歌舞伎の『花館愛護櫻』江戸山村座で初演。
江戸へ下った後の事件は?
- 正徳三年五月、伯父の梁川藩主の大久保松平義昌逝去。
- 通春(宗春)の側近であった御勝手番金森数右衛門吐血頓死。続いて同じく朝倉平左衛門が自害。
- 七月、藩主吉通薨去。
- 十月藩主五郎太薨去
- 継友藩主に。
- 十二月元服し、求馬道春に。
求馬の名は従兄梁川二代藩主大久保松平義方の通名。 - 兄は大大名級に出世するが通春(宗春)は三年間放っておかれる。
- 正徳四年(1714)一月から二月江島生島事件。
- 正徳六年(1716)将軍吉宗公が就任。
テレビドラマでは八代将軍徳川吉宗公と対立したとされますが、事実はどうですか?
- 宗春卿を部屋住みから尾張徳川家御連枝に引き上げたのは将軍吉宗公。
- 尾張にとって重要な官位である主計頭*)を授ける。
- 豊臣秀吉の子飼いで名古屋生まれで名古屋城築城の加藤清正
- 犬山初代藩主平岩親吉(家康長男信康・尾張初代藩主義直のお守役)
- 尾張徳川家御連枝時代の宗春は吉宗公によって特別に可愛がられた。
- 将軍吉宗公自ら鷹狩で獲った雁を数度賜る
(部屋住みとしては例外的な措置) - 江戸城内の行事に特別に参加した事例多数。
- 梁川藩主就任も尾張藩主就任も吉宗公の特別な計らい。
- 尾張藩主になった後も政策こそ異なれども直接的な対立は記録はない。
- 宗春は白牛に乗ったというが、白牛といえば当時は将軍吉宗が輸入したものであった。
- 宗春隠居後、吉宗公から拝領した人参を身近な場所で大切に育てる。
*)主計頭(かずえのかみ)
律令制からある官位で、今でいう財務大臣。当時の直近の例として
律令制からある官位で、今でいう財務大臣。当時の直近の例として
宗春卿は、なぜ将軍吉宗公と対立したと言われたのですか?
- 兄の継友卿が、将軍位に就けず、尾張藩から将軍位に就いたものが居ないから
尾張藩主は将軍位に就けなかったのではなく、就かなかった。
(家康以来、西方に対する拠点として尾張を治めることこそが徳川にとって第一と考えていたから) - 質素倹約の幕府に対して、規制緩和策を用いたから。
- 当時の質素倹約の幕府の評判は悪く、宗春卿の政策は広く庶民に受け入れられたから。
- 将軍吉宗公によって、隠居謹慎を命じられたから。
藩主就任まで、名古屋に戻ったことはないのですか?
- 梁川藩主に就任の前年に、母の病気という名目で三ヶ月帰国している。
- 直前に、姪の夫である権大納言九條幸教が薨去している・・
・・・・・・上洛した可能性あり - 帰国中に、姪の三姫が従弟の川田久保松平友淳(後の尾張藩八代藩主徳川宗勝)に嫁ぐ。
三姫は四代藩主の娘であり、大名でない御連枝に嫁ぐのは異例
梁川藩主時代の政策は?
- 人道に反する祭りは禁止した例:正月の水掛け・カセ鳥の窃盗。
- 不作時に種籾を放出させ飢餓をなくすつつこ引き祭りの始め。
- 医療の保護育成例:医学書の格安頒布。
- 六斎市(月六回の市)・馬市の奨励。
通説では、尾張藩主就任後の宗春卿は派手な衣装を着て花街で遊んだり お金を湯水のごとく使ったと評判が良くないのですが本当ですか?
- 宗春卿の当時の評判はとても良いものであった。
- 「京が興冷めした」
- 「世こぞって希代の名君と打ち寄せ打ち寄せ評判し」
- 「それに付き城下の繁昌も他国にならぶものなし」
- 「よく宗春卿の仁徳をしたいけるにや」
と言われるくらい、仁政をおこない尾張藩を盛り上げました。 - 庶民を喜ばせるために派手な衣装を着て演出したのは本当。
- お金を湯水のごとく使った記録はない。
- 花街や提灯は女性保護のため。
- 死刑を一人も出さなかった例:
- 名古屋心中(闇の森心中)
- 罰するのではなく罪を起こさない国造り例:
- 警邏隊を巡視させる
- 女性の保護と女性や子どもが夜でも歩ける街作り例:
- 提灯や花街の創設
- 幕府の命や財政よりも庶民の喜びを第一に。
- 意味のある祭りを盛んにし奨励した例:
- 東照宮祭・名古屋祇園祭(天王)・盆踊り等
- 身分を超える公平主義例:芝居小屋等では武士も町民も同じ座坪に。楽しみは身分に関係なく痛みは武士が負う。
- 庶民が喜ぶことをした例:
- 奴振り・白牛・漆黒の馬と衣装・派手な衣装
- 自分の身にあった遊びは大切であるとした例:
- 遊廓・芝居・見せ物等
- 衣服・家・持ち物等は禁制のある物以外は自由にした例:
- 條々二十一箇条等
- ファッションリーダーを自ら担った例:
- 申楽(能・狂言)・歌舞伎・朝鮮使節団等の衣装等
- 心を込めた贈答・饗応を大切にした例:
- 條々二十一箇条等
- 形式よりも中身を大切にした例:
- 仁・「まこと」を重視する温知政要・條々二十一箇条等
- 法律や規制は少ないほうが良いとした例:
- 規制緩和温知政要・條々二十一箇条等
- 簡単なミスの訴状等の書類を差し戻さず受け入れるように指示した條々二十一箇条等
- 庶民と上級藩士が出会う場を提供した例:
- 御下屋敷や市谷邸のお披露目等
- 商人との対話を積極的にした例:
- 岐阜巡行・乾御殿や御下屋敷滞在時
- 奪い合うことや義に合わぬことを禁止した例:
- 條々二十一箇条等
- マニフェストであり家訓でもある『温知政要』を執筆し上級家臣に配布。
 よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)
よろしければ、この拍手ボタンを押して下さい(書込みもできます)