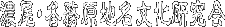定例講演年次計画
(講師名敬称略)
◆令和6年度定例講演会(予定)◆
開演時間は13:30
| 4/20 (土) (産ア) |
『古墳分布から見た地域構造の変化と
古墳築造集団の性質(仮)』
各務原市内には、600基以上の古墳が築造された。前方後円墳や群集墳の展開から地域構造の変化をとらえ、
古墳分布のあり方や立地条件から古墳築造集団の性質を考察する。
|
各務原市文化財課 課長 西村 勝広 |
|---|---|---|
| 6/15 (土) (産2F) |
『各務原市における水害と治水、
そして水防災を考える』
各務原市で水害があるのか? 木曽川・境川・長良川による水害の心配はないのでは?
と、考えているあなたに来てほしい講座です。 過去の災害から何を学ぶか、リスク・災害・ハザードの違い、ダムや堤防の強化から転換した新しい考え方 「流域治水」とは何か、など。 災害は忘れた「と」ころにやってくる! |
名古屋大学 減災連携研究センター 特任 教授 田代 喬 専門:河川工学・ ライフ ライン 水防災など |
| 8/17 (土) (産ア) |
『山と川と海の循環』
−里山林と粗朶の生産・利用
自然(水・空気・森)と人間との関係を、里山林の視点から考えてみる。
里山の保全を、理念だけでなくコストも考えて、どう実現するのか・・・。 昔、おじいさんは山へ柴刈りに行った。現代の海でも、海苔ソダを見かける。 河川の護岸工事では、粗朶を使う工法がある。粗朶を作る人と使う人はどう繋がるか。 (粗朶の読みは「そだ」。伐り取った木の小枝のこと) |
岐阜県立森林文化 アカデミー 教授 柳沢 直 (専門:植物生態学) |
| 10/19 (土) (産2F) |
『生活に役立つ和算』
−あなたもこれで数学好きに
和算とは、江戸時代に盛んになった算術である。田畑の広さの算定、暦をつくるための天文測量、お金の勘定など、
実用上の必要から生まれたものだ。社寺に奉納された「算額」は、和算好きによる知恵比べのゲームだ。 2回目の今回も、数学嫌いの方にも楽しめる話題を提供したい。 |
ツボウチ塾 塾頭 坪内 和俊 |
| 12/21 (土) (産ア) |
『県の石、 中部 ・東海 地方を例に』
−翡翠は日本の国石−
当日皆さんからのアンケート結果をもとに、県の石(日本地質学会選定)からいくつかを選び、
それらのでき方、各地域の地質との関係や、人間の歴史との関わりについてお話しします。 新潟県の石、そして日本の国石ヒスイ(日本鉱物科学会選定)。ヒスイを探すとき、 それとよく似たきつね石などに化かされないための簡単な実験を、台所にあるものを使って皆さんと一緒に行ってみましょう。 |
名古屋大学 名誉教授 榎並 正樹 (専門:岩石学) |
| 2/15 (土) (未) |
『名勝となった木曽川』
昭和6(1931)年5月11日、木曽川のうち可児市〜各務原市・犬山市の流域は、
わが国の優れた国土美を表すものとして国の名勝に指定された。
「名勝 木曽川」の美しい風景はどのように見出され、指定後はどのように保護・活用されてきたか。
木曽川を取り巻く自然的・歴史的環境を概観し、文化財とは何かを考える。
|
各務原市文化財課 指導主事 福井 隆士 |
|
*印はは第4土曜日ですのでご注意ください。 講演会場が変更されている場合は赤字になっています。 |
||
諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2024/2/7更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 (4階多目的ホール) |
(産ア) | 各務原市産業文化センター (1階あすかホール) |
|---|---|---|---|
| (産2F) | 各務原市産業文化センター (2階の第3会議室) |
(未) | 未定 |
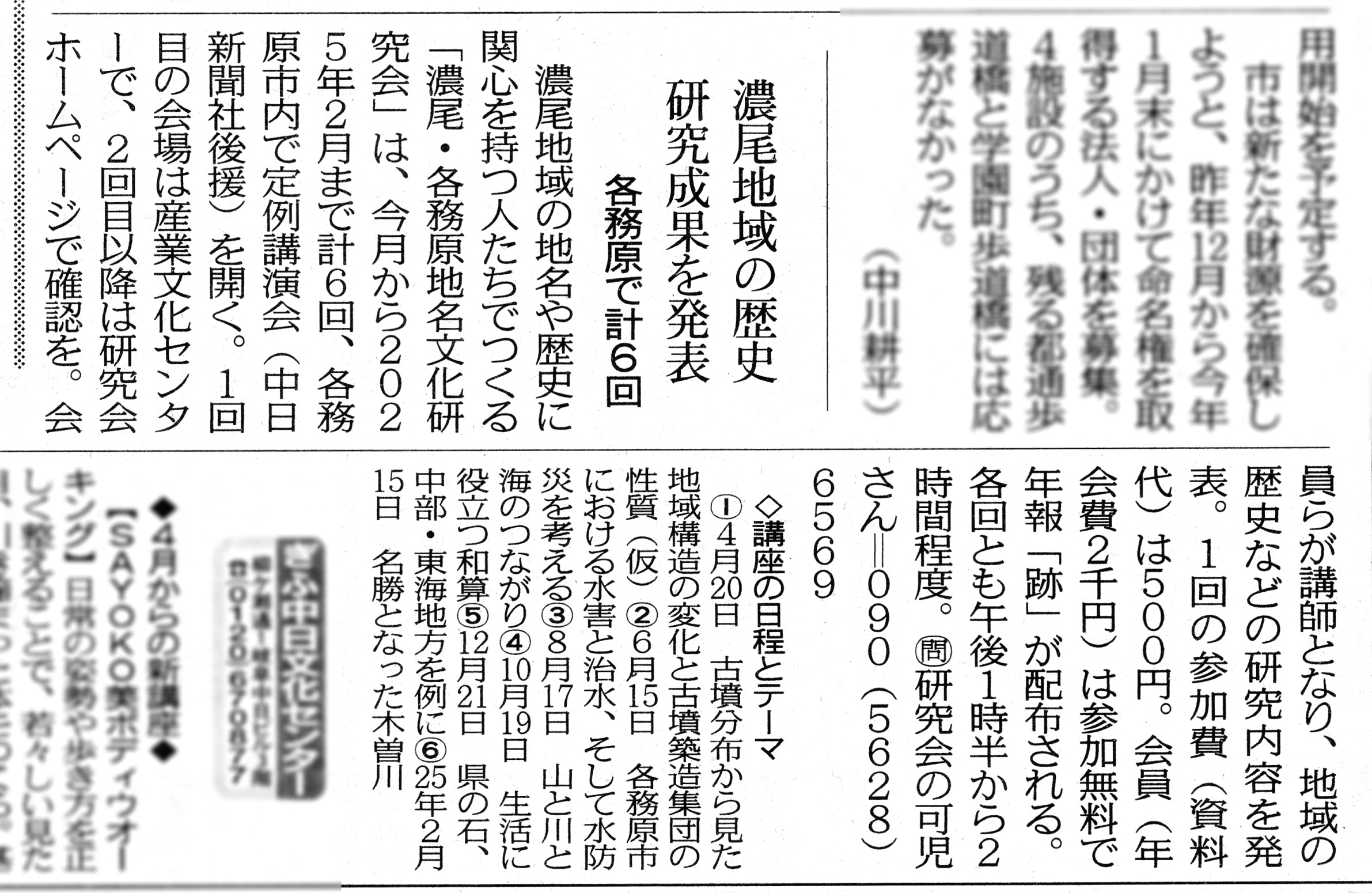
中日新聞2024年4月10日岐阜近郊版
◆令和5年度定例講演会(予定)◆
開演時間は13:30
| 4/22 (土 (図) |
『江戸時代に破壊された各務野の古墳』
1799年(寛政11年)の秋、各務野の「古塚」は約200基破壊されました。
それは何故か、何が出土したか等、好古家の記録から語ります。
また幕末の尾張藩の学者による各務原の旧跡巡りも解説します。
|
各務原市文化財課 歴史民俗資料館 学芸員 長谷 健生 |
|---|---|---|
| 6/17 (土) (産2F) |
『美濃赤坂の金生山と化石』
−古生物学発祥の地−
金生山では石灰石を採掘しているが、そこにはフズリナ・ウミユリ・サンゴ・シカマイア(二枚貝)などの
化石が多数含まれている。それらの海の生物は、一体いつの時期にどこに生息していたのか。
どのようにして化石となり、山となったのか。 化石を通して分かる地球の歴史について話します。 |
(岐阜県) 地名文化研究会 会長 説田 武紀 |
| 8/19 (土) (産2F) |
『中山道をよむ −地図と地形−』
1万分1地形図にこだわり、街道の歴史的な蘊蓄を丹念に歩いて集め、手に持てる大きさの折本にした
『ホントに歩く中山道』を出版しているのが、風人社である。ウォークマップをつくる中で気づいた、
街道と地形の関わりや地図の魅力を、中山道を通して語る。
|
風人社 社長 大森 誠 |
| 10/21 (土) (産2F) |
『どこの家にもある各務原の歴史 』
母が他界し、蘇原大島町の家を整理すると、先祖と地域の歴史にまつわる様々な資料が出てまいりました。 横山忠三郎(曽祖父)は、明治期に各務用水の建設に関わり、多賀治(祖父)は、 大正期から昭和前半に福沢桃介や川上貞奴と交わり、木曽川の電源開発や旧蘇原町の政治に携わりました。 信三(父)は、戦時中に川崎航空機と陸軍航空本部で戦闘機の開発に関わりました。 どこのお宅にも歴史があり、それが地域の歴史となって今日の各務原があるのであろう、との感慨を皆様と共有したいと思います。 |
中部大学 客員教授 横山 信治 |
| 12/16 (土) (産2F) |
『隕石:地球と宇宙をつなぐ石』
地球が46億年前に誕生したとする根拠は、46億年前の石が見つかったからなのか。
落ちてきた隕石と普通の石は、どう見分けるのか。
美濃隕石(1909年 、現在の岐阜市〜美濃市の辺りに多数の隕石が落下)はどんな隕石なのか。
地球上の生命の起源は、地球外(隕石)からか。鉄隕石と地球の核は、組成がソックリ?など、
隕石が語る地球と宇宙の歴史を解説します。
|
名古屋大学 名誉教授 足立 守 |
| 2/17 (土) (産2F) |
『福沢桃介の人脈と 名古屋経済基盤づくり』 −下出民義・義雄父子と「大同町」−
福沢桃介の番頭として中部経済界で活躍した下出民義は、教育界では東邦商業学校を創立した。
子の義雄は、戦前の大同製鋼の基礎を固め、名古屋市南区の町名「大同町」の由来となっている。 この父子の足跡から見えてくるものとは。 |
中部産業遺産研究会 会員 朝井 佐智子 |
|
*印はは第4土曜日ですのでご注意ください。 講演会場が変更されている場合は赤字になっています。 |
||
諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2023/12/18更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 (4階多目的ホール) |
(産ア) | 各務原市産業文化センター (1階あすかホール) |
|---|---|---|---|
| (産2F) | 各務原市産業文化センター (2階の第3会議室) |
(未) | 未定 |
◆令和4年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/23
(土 (産2F) |
『伊木清兵衛を探して』
二年前の講演 「伊木清兵衛と戦国の各務原」 は、数々の反響を呼んだ。その第二弾。 池田家に仕え活躍した戦国武将、伊木清兵衛。その生涯の転機はいつも濃尾国境での合戦だった。 清兵衛とその子孫たちの足跡をたどるとともに、中世の各務原の戦略的価値を考える。 |
各務原市文化財課 歴史民俗資料館 学芸員 長谷 健生 |
|---|---|---|
| 6/18 (土) (産2F) |
『戦国から江戸期の美濃方言』
−ことばの時代考証−
時代劇を見ていて、あのような言葉が話されていただろうかと疑問が湧くことがあります。
そこで今回は、過去の岐阜方言を取りあげます。昔の方言をどうやって知るのか。
方言は時代によりどれくらい変わったのか。そもそも、方言はいつ頃からあるのか。
美濃方言に誇りが持てるような話ができればと思います。
|
岐阜大学教育学部 教授 山田 敏弘 |
| 8/20 (土) (産ア) |
『美濃各務の古墳勢力の萌芽と展開』
古墳時代に入ると、境川流域に発達した勢力は、中央との結びつきを強化して支配圏を固め、
その象徴となる坊の塚古墳を築造した。鵜沼地域を尾張圏だとする説に対し、美濃圏である見解を論じるとともに、
美濃勢力が尾張に拡大した事例も検証する。
|
各務原市文化財課 課長 西村 勝広 |
| 10/22 (土 (図) |
(仮)『吉田初三郎の 鳥瞰図に見る犬山・各務原 』
関東大震災後、初三郎は犬山に招かれて画業を続けた。
1600点と言われる鳥瞰図を題材に、大正〜昭和の地方都市(犬山、日本ラインなど)の何をどう描いたか。
地形・建築・観光・鉄道など多面的な視点から検証する。
|
名古屋大学大学院 環境学研究科 准教授 堀田 典裕 |
| 12/17 (土) (産ア) |
『付加体造山論 発祥の地、 美濃の山の成り立ちを探る』
山のでき方には二つのタイプがあります。海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むタイプと、
大陸プレート同士がぶつかり合うタイプです。どうしてそんな事がわかるのか、
前者のタイプを中心に、ロシア・中国などの海外フィールドワークでの体験を交えながら、
美濃の山の成り立ちについて話します。
|
岐阜大学工学部 教授 小嶋 智 |
| 2/18 (土) (産2F) |
『鵜沼地区における「尾張文化」』
鵜沼では、名古屋市へ通勤する人が少なくありません。これは電車通勤が可能との理由だけからなのか?
鵜沼地区を中心に、見て歩きの中での気づき(尾張造など)を通して、
「尾張文化」の影響を探り、美濃と尾張について考える。
(尾張造:神社の建築様式)
|
当研究会 理事 安田 修司 |
|
*印はは第4土曜日ですのでご注意ください。 講演会場が変更されている場合は赤字になっています。 |
||
諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2022/8/24更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 (4階多目的ホール) |
(産ア) | 各務原市産業文化センター (1階あすかホール) |
|---|---|---|---|
| (産2F) | 各務原市産業文化センター (2階の第3会議室) |
(未) | 未定 |
◆令和3年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/17
(土) (産) |
『ガケ(崖)と各務原』
各務原は、山・川・谷など起伏に富んだ地形であり、また旧石器時代〜現代まで長期にわたり
人間が住んできた地域です。今回、数多くの発掘に関わってきた経験から、
ガケ(崖)地形という新たな切り口で、各務原の歴史と特徴についてお話します。
中止
|
各務原市文化財課 課長 西村 勝広 |
|---|---|---|
| 6/12 (土 (産) |
『福沢桃介の人脈と 名古屋の経済基盤づくり』 −下出民義・義雄父子と「大同町」−
福沢桃介の番頭として中部経済界で活躍した下出民義は、教育界では東邦商業学校を創立した。
子の義雄は、戦前の大同製鋼の基礎を固め、名古屋市南区の町名「大同町」となっている。
この父子の足跡から見えてくるものとは・・ (下出:しもいで)
|
中部産業遺産研究会 会員 朝井 佐智子 |
| 8/14 (土 (図) |
『坊の塚古墳から何が分かったか』 −発掘の成果と今後の課題−
5年におよぶ発掘によって、後円部へ登る道の確認、前方部と後円部の境目にある葺石の
基底石から古墳の作られ方を解明するなどの大きな成果があった。 成果と共に、新たに生まれた疑問やこれからの課題について、詳しくお話しします。 |
各務原市文化財課 埋蔵文化財調査センター 学芸員 近藤 美穂 |
| 10/16 (土) (産2F) |
『変成岩から地球を探る 』 −プレート運動と日本列島の地下−
地球の表面は、14−15枚のプレートに覆われており,それらの移動により、地震や火山活動などの現象が起きます。
海底の大山脈で生まれた海のプレートは、長い旅路の果てに地球内部に戻ってゆきます。
そんな場所が私たちの足下にあります。しかし地下深くの試料採取は、月や小惑星リュウグウよりもはるかに困難です。
地球内部に何があり、どんなことが起こっているかは、どうしたら判るのでしょうか。 「変成岩」をキーワードにお話しします。 |
名古屋大学 名誉教授 榎並 正樹 |
| 12/18 (土) (産2F) |
『土を見て、考える』
2年前には、各務原の黒ボク土の話をしました。 今回は、1年間の米国体験を交えた土の日米比較、水田から発生するメタンを活用する研究 (地球温暖化の一因からエネルギー源として)など、土にまつわる話題を、縦横にわかりやすく解説します。 |
名城大学農学部 准教授 村野 宏達 |
| 2/20 (日) (図) |
『戦国から江戸期の美濃方言』 −ことばの時代考証−
時代劇を見ていて、あのような言葉が話されていただろうかと疑問が湧くことがあります。
そこで今回は、過去の岐阜方言を取りあげます。
昔の方言をどうやって知るのか。方言は時代によりどれくらい変わったのか。そもそも、方言はいつ頃からあるのか。
美濃方言に誇りが持てるような話ができればと思います。
中止
|
岐阜大学教育学部 教授 山田 敏弘 |
|
*印はは第2土曜日ですのでご注意ください。 講演会場が変更されている場合は赤字になっています。 (産2F)は産業文化センター2階、第3会議室です。 |
||
諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2021/11/20更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 (4階多目的ホール) |
(産) | 各務原市産業文化センタ- (1階あすかホール) |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (未) | 未定 |
◆令和2年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/18 (土) (図) |
『伊木清兵衛と戦国の各務原』
伊木山城主であったとされる伊木清兵衛とは、何者か。
彼に関する全国の資料を探す中で、戦国の各務原に領地をもった武士の姿が見えてきた。 小牧・長久手の戦いや関ヶ原の戦いでは、各務原において、誰と誰がどこで戦ったのか。 永井氏や安積氏といった戦国以来の有力者についても言及する。 中止
中止
中止
順延
|
各務原市文化財課 歴史民俗資料館 学芸員 長谷 健生 |
|---|---|---|
| 6/20 (土) (図) |
『福沢桃介の人脈と 名古屋の経済基盤づくり』 −下出民義・義雄父子と「大同町」−
福沢桃介の番頭として中部経済界で活躍した下出民義は、教育界では東邦商業学校を創立した。
子の義雄は、戦前の大同製鋼の基礎を固め、名古屋市南区の町名「大同町」となっている。
この父子の足跡から見えてくるものとは・・ (下出:しもいで)
|
中部産業遺産研究会 会員 朝井 佐智子 |
| 8/15 (土) (図) |
『戦時の記憶』 Part5
5年目となる今回の話し手は、昨年に引き続いて永井 章一氏。時間不足で話し足りなかった終戦に近い時期を中心に語っていただく。 聞き手は、各務原市の歴史に詳しい各務原市文化財課課長の西村 勝広氏が担当する。 |
|
| 10/10 (土) (産) |
『チャートに育まれた各務原・犬山』
−世界が注目する放散虫・・
ウヌマ エキナタスとは−
ウヌマの学名がついた放散虫が、木曽川の石から見つかっている。
1.7億年前に生きていた原生生物である。 各務原や日本列島の成り立ちを、岩石・地質・地層の視点から、わかりやすく解説する。
放散虫:海のプランクトンの一種
チ ャ ー ト:放散虫などからできた堆積岩 |
名古屋大学 特任教授 名古屋経済大学 客員教授 足立 守 |
| 12/12 (土) (産) |
『伊木清兵衛と戦国の各務原』《変更》
伊木山城主であったとされる伊木清兵衛とは、何者か。
彼に関する全国の資料を探す中で、戦国の各務原に領地をもった武士の姿が見えてきた。 小牧・長久手の戦いや関ヶ原の戦いでは、各務原において、誰と誰がどこで戦ったのか。 永井氏や安積氏といった戦国以来の有力者についても言及する。 ⇒講演会レジュメのダイジェスト版
(別ウインドウ) |
各務原市文化財課 歴史民俗資料館 学芸員 長谷 健生 |
| 1/30 (土) (産) |
『坊の塚古墳から何が分かったか』
−発掘の成果と今後の課題−
5年におよぶ発掘によって、後円部へ登る道の確認、
前方部と後円部の境目にある葺石の基底石から古墳の作られ方を解明するなどの大きな成果があった。 成果と共に、新たに生まれた疑問やこれからの課題について、発掘担当者が詳しく、そして熱く語る。 |
各務原市文化財課 埋蔵文化財調査センター 学芸員 近藤 美穂 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2020/12/14更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 (4階多目的ホール) |
(産) | 各務原市産業文化センタ-> (1階あすかホール) |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (未) | 未定 |
◆平成31年度(令和元年度)定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/20 (土) (図) |
『古東山道と各務原の古墳群』
美濃・尾張國が成立する以前,木曽川流域に存在したであろう個性的な部族社会。
その実態を集落遺跡や古墳の分布などから読み解き,「美濃」でもなく「尾張」でもない,
もう一つの地域社会の存在を考えてみたい。
そこには現在に通じる生活圏を含めたまとまりある一つの基層文化が見えてくる。 |
NPO法人 古代邇波の里・ 文化遺産ネットワーク 理事長 赤塚 次郎 |
|---|---|---|
| 6/15 (土) (図) |
『各務原台地14万年の物語』 −その形成過程と歴史に及ぼしたもの−
本市の歴史的な特性を調べていくと、各務原台地の存在に行き着く。
木曽川による台地の形成過程と、台地を取り巻く環境下で展開したドラマチックな歴史を探る。 |
各務原市文化財課 課長 西村 勝広 |
| 8/17 (土) (図) |
『戦時の記憶』Part4
4回目となる今回は、平成生まれの若き学芸員が聞き手となって、戦時体験者の記憶を掘り下げていきます。 |
(コーディネーター) 各務原歴史民俗資料館 学芸員 長谷 健生 |
| 10/19 (土) (図) |
『長良川が育んだ弥勒寺遺跡群』 〜史跡と円空と鵜飼〜
国指定史跡弥勒寺官衙遺跡群は、小瀬鵜飼の開催地として知られ、また、円空が入定した地。
彼が中興した弥勒寺は、今もその法灯を灯し続けています。 |
関市文化財保護センター 所長 田中 弘志 |
| 12/14 (土) (図) |
『濃尾地震と近代日本』
濃尾地震は明治維新以来様々な課題を経て近代国家として確立した日本を襲った災害でした。
濃尾地震が社会に与えた影響や、その後、どのように語られていったのかを紹介します。 |
尾西歴史民俗資料館 学芸員 宮川 充史 |
| 2/15 (土) (未) |
『福澤桃介と木曽川水系の電源開発』
木曽川の水力発電で電力王と呼ばれた桃介。ダム建設による農業用水への影響。それによって生じた深刻な対立。
電力の多くが何故遠方の関西圏に送られたのか。
実現はしなかった貞照寺周辺の遊園地計画や鵜沼を含む新工業地帯を構想とは・・ |
中部産業遺産研究会 副会長 浅野 伸一 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2019/7/28更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 | (産) | 各務原市産業文化センター |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (未) | 未定 |
◆平成30年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/21 (土) (図) |
『ジオとして見た濃尾平野と木曽川』
ジオの視点から濃尾平野における 木曽川の役割、特に岐阜県側から みた役割ついて解説 |
岐阜大学名誉教授 小井土 由光 |
|---|---|---|
| 6/16 (土) (図) |
『和算−世界に誇る江戸の算術』 ・・・趣味か遊びか、オタク和算家たちも |
ツボウチ塾・塾長 坪内 和俊 |
| 『彦坐王から日本武尊への系譜』 〜狭穂彦王の叛乱 |
各務原歴史研究会会長 瀬川 照子 |
|
| 8/18 (土) (図) |
『昭和レトロの那加町』 〜建築からみた街(まち)の歴史 |
各務原市西ライフ課長 川上 光洋 |
| 『戦時の記憶』(第3回) コーディネーター (本研究会顧問)松尾 裕 |
戦時体験者の皆さん |
|
| 10/20 (土) (図) |
『木曽川と農業用水』 〜尾張農業用水の歴史と文化 |
(株)エース 技師長 清水 正義 |
| 『各務原台地の黒ボク土』 〜全国的に見る黒ぼく土との関係 |
名城大学農学部准教授 村野 宏達 |
|
| 12/15 (土) (図) |
『方言について』 〜文化という観点から 東西の方言を併せもつハイブリッドな 岐阜の方言の魅力とは・・ |
岐阜大学教育学部教授 山田 敏弘 |
| 2/16 (土) (図) |
『くすりの歴史』 〜認知症になりにくい食生活 草で楽(らく)になると書いて「薬」 そんな薬草から始まったくすりの歴史 そして未知なる病「認知症」とは… |
内藤記念くすり博物館館長 森田 宏 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2018/12/15更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 | (産) | 各務原市産業文化センター |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (未) | 未定 |
◆平成29年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/15 (土) (福) |
続・各務原地名 | 教育委員会事務局文化財課課長 西村 勝広 |
|---|---|---|
| イタリアの文化と日本の文化 | 岐阜大学教育学部教授 山田 敏弘 |
|
| 6/17 (土) (交) |
続・各務原市から展開する古代地名 | 各務原歴史研究会会長 瀬川 照子 |
| 犬山城と成瀬家 | 犬山城白帝文庫理事長 成瀬 淳子 |
|
| 8/19 (土) (産) |
朝日町町史編纂 | 元朝日町自治会連合会長 谷内 朗 |
| 戦時の記憶 | 歴史街道を歩く会会長 足立 勘二 |
|
| 10/21 (土) (交) |
尾張に於ける倭姫命の伝説 | 一宮郷土研究会会員 小川 克子 |
| ”天王地名”に思う | 本研究会理事 安田 修司 |
|
| 12/16 (土) (産) |
木曽川がつくった地形と地名 | 本研究会副会長 松尾 裕 |
| 万葉集と岐阜の地名 | 聖徳学園大学短期大学部講師 稲垣 和秋 |
|
| 2/17 (土) (交) |
川島の地名と由来 | 笠松力検定委員会委員 小川 敏彦 |
| やさしい河川工学 | 岐阜県地名文化研究会副会長 三澤 博敬 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2017/4/15更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 | (産) | 各務原市産業文化センター |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (交) | 鵜沼西町交流館 |
◆平成28年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/16 (土) (福) |
漢字一字に込めた想い | 各務原市長 浅野 健司 |
|---|---|---|
| 地名とことば | 岐阜大学教育学部教授 山田 敏弘 |
|
| 6/18 (土) (交) |
五重塔の歴史と耐震性 | 立命館大学名誉教授 早川 清 |
| 音律と度量衡 | 愛知地名文化研究会副会長 奥田 昌男 |
|
| 8/20 (土) (産) |
戦時の記憶 コーディネーター (本研究会副会長)松尾 裕 |
戦時体験者の皆さん |
| 地名に見る各務原台地の開拓史 | 教育委員会文化財課課長 西村 勝広 |
|
| 10/15 (土) (交) |
忘れられた街道と地名 | 愛知地名文化研究会会長 中根 洋治 |
| 切手と地名 | 土木学会名誉会員 部田 哲雄 |
|
| 12/17 (土) (産) |
金生山化石と赤坂地名 | 岐阜県地名文化研究会会長 説田 武紀 |
| 地盤力学から見た濃尾平野 | 名古屋大学院教授 中野 正樹 |
|
| 2/18 (土) (交) |
尾張藩主の墓石は鵜沼石だった | 高野山真言宗/高家寺住職 北川 宥智 |
| 美濃路と中山道 | 尾西歴史民俗資料館学芸員 宮川 充史 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2016/4/16更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 | (産) | 各務原市産業文化センター |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (交) | 鵜沼西町交流館 |
◆平成27年度定例講演会(終了)◆
開演時間は13:30
| 4/18 (土) (交) |
各務原という地名 | 歴史民俗資料館館長 西村 勝広 |
|---|---|---|
| 月に地名を残した日本人 | 本研究会会長 可児 幸彦 |
|
| 6/20 (土) (交) |
日本人のルーツとマンモスの絶滅 | 立命館大学名誉教授 早川 清 |
| 十万年前の川の跡・うとう峠 | 愛知地名文化研究会会長 中根 洋治 |
|
| 8/15 (土) (産) |
零戦と各務原/ゼロ戦の秘話 | 本研究会副会長 松尾 裕 |
| 災害立国日本/災害地名の実情 | 岐阜県地名文化研究会副会長 三澤 博敬 |
|
| 10/17 (土) (交) |
各務原から展開する古代地名 | 本研究会副会長 瀬川 照子 |
| 私が巡った外国の地名 | 愛知地名文化研究会副会長 奥田 昌男 |
|
| 12/19 (土) (産) |
あの世の地名 | 愛知地名文化研究会事務局長 大山 英治 |
| 美濃紙 | 元美濃市教育長 川嶋 智孝 |
|
| 2/20 (土) (交) |
木遣音頭と「がんどばぼち」 | 中山道鵜沼宿 まちづくりの会会長 安田 新作 |
| 食・中山道・かかみがはら | 中山道鵜沼宿 ボランティアガイドの会会長 近藤 章 |
*諸般の事情によっては講演会場、講演内容・講師等が変更になる場合もございます。
(2015/4/18更新)
| ▲講演会場 | |||
| (図) | 各務原市中央図書館 | (産) | 各務原市産業文化センター |
|---|---|---|---|
| (福) | 総合福祉会館 | (交) | 鵜沼西町交流館 |